2024-03-21
時間術についての認識が変わる本。YOUR TIME を読んだ
YOUR TIME ユア・タイム: 4063の科学データで導き出した、あなたの人生を変える最後の時間術 を読みました。
これまでの時間術についての認識が変わる良い本でした。
備忘録がてらのメモです
現代人は常に時間に追われ、やることはたくさんあるのに時間がない、という感覚に襲われがちです。
そんな流れを受けて、これまであらゆる時間術が生まれてきました。
しかし、実は時間の効率を追い求めるほど、逆に時間が不足していき生産性がどんどん下がってしまうのです。
この本では、そういった時間術の罠を紹介し、どうすれば時間の余裕を取り戻し有意義な時間を増やせるのかを教えてくれます。
- 時間術を駆使してもパフォーマンスはさほど上がらない
- 最新の研究によると時間術と仕事のパフォーマンスの相関は弱い
- 万人に効く時間術はなく、どれも一部の人にしか効果がない
- 仕事のパフォーマンスよりも人生の満足度との相関が強い
- 自分の人生をコントロールできている感覚が生まれるので、パフォーマンスを上げるものというより主観的な幸福度を上げるもの
- 最新の研究によると時間術と仕事のパフォーマンスの相関は弱い
- 時間の効率を気にするほど作業の効率は下がる
- 複数のタスクを処理することで、脳のキャパを超えてしまい判断力が下がる(トンネリング)
- 手軽なタスクに多くの時間を費やしてしまう
- 長期的な目線が失われ、戦略的な計画が立てられなくなる
- 創造性が下がる
- 創造的なアイディアはリラックス状態になったときに出るため、効率を求めて集中状態が続くと良いアイディアが出てこない
- ストレスが多く心身を擦り減らす
- 高い目標や生産性を重んじる職場環境ほど、従業員のストレスが多くメンタルが病みやすい
- 答えをすぐ求めずに曖昧さを放置できる能力(認知の耐性)が下がる
- 認知の耐性がない人ほど深い思考ができておらず、創造的なアイディアを出すのが苦手で、メンタルを病みやすい
- 大量の情報を短時間でインプットしても、内容は頭に残らない
- 一定時間に脳が処理できる情報にはキャパがあり、それを超えても処理ができない
- ひとつひとつへの注目度が下がり、後から思い出せなくなる
- たいしたことをしていないのに時間だけが過ぎた感覚にもつながる
- 複数のタスクを処理することで、脳のキャパを超えてしまい判断力が下がる(トンネリング)
- 生産性を上げるほど忙しくなる
- 生産性の高い人に、より仕事が集中する
- 仕事をした結果、さらなる次の仕事が生まれる
- いくつかタスクをこなしても、手付かずの残りのタスクに意識が向かう
- 自分の個体差を知り、本当に自分に効く時間術を知る
- 時間効率を追い求めるのをやめ、本当に大事なことに時間を使う
- 時間の余裕を取り戻す方法を知り、自分の能力をフルに発揮できるようにする
- 既存の時間術で万人に効果があるものはなく、どれも一部の人にのみ効果がある
- それはヒトの個体差によるもの
- 特に、時間の使い方において、パフォーマンスに影響を与えるのは「予期」と「想起」の能力
- 「予期」とは、未来を想像する能力
- 「想起」とは、過去を想像する能力
- この2つの能力は時間術によって調整可能だが、もともとちょうど良い場合は時間術を使っても意味がない
- 自分がこの二つの能力においてどういう個体差を持っているかを知ることで、使うべき時間術が見えてくる
- 時間感覚タイプテスト
- 「予期」は濃淡と多寡がある
- 予期が濃い人ほど将来に現実感を持つことができ、薄い人ほど将来とのつながりを感じられない
- 予期が多い人ほどすべきことのイメージが多く頭に浮かび、少ない人ほどすべきことが明確
- 「想起」は正誤と肯定的/否定的がある
- 想起が正しい人ほど将来のタスクの見積もりがうまく、誤っている人ほど見積もりが苦手
- 想起が肯定的な人ほど自信を持つことができ、否定的な人ほど将来のタスクにもネガティブな感情を持つ
- 「予期」は濃くて少ない、「想起」は正しくて肯定的、の方がパフォーマンスが高いが、どれも行きすぎると副作用が出る
- 例えば想起が肯定的すぎる場合、過剰に自信を持ってしまうので、次もなんとかなるだろうと準備をしない。
- 将来の自分とのつながりが感じられないので、将来のためになにかを行うことができない
- 必要だが嫌なこと、面倒なことに取りかかれない
- 喫煙やアルコールといった、副作用があるような手軽な快楽に手を出してしまう
- 運動のような将来のための習慣が続かない
- 予期が薄い場合の戦略
- タイムボクシング
- あらかじめタスクに時間を割り当てておき、その枠内で作業を終わらせるようにする
- 事前に決めた時間に達したら、まだ作業が終わっていなくても切り上げなければならない
- 手順
- 取り組むタスクを決める
- いつまでになにを達成したいかの目標を決める
- 必要な時間を割り出し、カレンダーにそのタスクをやる時間を登録する(ボックス)
- 1日が終わったら結果の評価をし、終わらなかったものは翌日のボックスに再配分する
- アンパッキング
- 作業を細かなステップに分解する
- ビジョン・エクササイズ
- タスクの締め切り直前にいる自分を想像する
- 手順
- タスクを選ぶ
- リラックスするまで深呼吸を繰り返す
- 締め切り直前にいる自分を3〜7分想像する
- ロールレンダリング
- 将来の自分に手紙を書く
- 手順
- 3年後の自分に悩みを相談する手紙を書く
- 3年後の自分になったつもりで返事を書く
- デイリーメトリクス
- 締め切りまで長い場合、締め切りまでの時間を日単位で表現する
- 例:3ヶ月→90日
- タイムボクシング
- 将来の目標から外れる行為を悪だと感じ、今を楽しめない
- 余暇を犠牲にするため、人生を楽しめていないと感じ、後から後悔してしまう
- ワーカホリックになりやすく、運動不足など不健康な生活をしてしまう
- 体調を崩したり燃え尽き症候群になる
- 予期が濃い場合の戦略
- プレコミットメント
- 事前に遊びのスケジュールを決めておく
- リマインディング
- 将来どのくらい後悔しそうかを考える
- ビジュアライズ
- 今のペースを続けたら1ヶ月ごとにどうなるかを考える
- 機能的アリバイ
- 正当な理由があるのだから生産性がない行為をしても良いというアリバイを自分に与える
- 生産性や効率とは無関係な、自分へのご褒美を設定する
- 金銭的に得をしたと感じられる状況で贅沢な遊びをする
- 正当な理由があるのだから生産性がない行為をしても良いというアリバイを自分に与える
- プレコミットメント
- やるべきイベントの数が多すぎて、意識があちらこちらに目移りしてしまい、タスクの処理能力が下がる
- 迷いが多くなる
- ゴールへのルートが多くなる
- 予期が多すぎる場合の戦略
- SSCエクササイズ
- 手順
- やるべきタスクを全てリストアップする
- 以下の質問をして点数をつける
- 周りが喜んでくれるか?4点
- どのくらい緊急か?4点
- 成功者になってもやるのか?5点
- 手伝ってくれる人がいたら任せるか?5点
- 点数を合計し、10点以下のものを以下のカテゴリーに分類する
- 放棄タスク
- 委任タスク
- 内容修正タスク
- 手順
- 切り替え速度を上げる
- 大事なタスクに集中する、と明確な意思確認をすることで、重要度が低いタスクに惑わされないようにする
- 手順
- 仕事で重要な問題を3つ選ぶ
- プライベートで重要な問題を3つ選ぶ
- 1,2の問題を書き出し、「重要な問題に集中することを許可します」と書き込む
- 熟慮プランニング
- 不慮のトラブルに強くしておく
- 手順
- 「何かトラブルが起きたときや状況が悪くなったときは、いったん立ち止まって対策をよく考える」という熟慮をプランニングしておく
- 障害プランニング
- 不慮のトラブルに強くしておく
- 手順
- その日に起きそうな問題をあらかじめ考えておき、対策を立てておく
- SSCエクササイズ
- 記憶の誤りが大きすぎて、現実味のない計画を立ててしまう
- 想起の誤りが大きい場合の戦略
- タイムログ
- 自分がどう時間を使ったかを記録する
- 手順
- 何かをするたびに時間、行動、効果を細かく書き入れる
- 1〜2週間を目安にデータを収集する
- 新たに計画を立てるときはタイムログをもとにたてる
- 他人に時間を見積もってもらう
- 第三者のほうが時間の見積もりがうまい
- コピー・プロンプト
- うまくやっている人を真似する
- 手順
- タスクを決める
- そのタスクをうまくやり遂げている人を探す
- その人がどのようにタスクをこなしているのかを調査する
- 真似してみる
- タイムログ
- 何の根拠もないのに「前もうまくいったから次もどうにかなる」と考えてしまう
- 適切なレベルであれば良いことだが、行き過ぎると失敗につながる
- 想起が肯定的すぎる場合の戦略
- タイムログ・アドバンス分析
- タイムログを分析する
- 手順
- タイムログをカテゴリー分けする
- タイムログを計算する
- 無駄な時間をチェックする
- 対策をプランニング化する
- 誘惑日記
- 誘惑に負けた体験を記録する
- ごまかし率を計算する
- 手順
- タスクの見積もりをする
- 完了までにかかった時間を記録する
- 見積もりの合計と実際の値の合計を割ってごまかし率を出す
- タスクを見積もる際はごまかし率をかけるようにする
- 手順
- 想起リライティング
- 過去の失敗に囚われないようにする
- 手順
- 失敗に終わった過去の行動を思い浮かべる
- 自分がどのように行動したかを頭の中で再現する
- いまならどう対処できただろうかと考える
- 3で思いついた案を使って、見事に解決した姿を思い描く
- タイムログ・アドバンス分析
- 過去をネガティブに捉えてしまい、自己効力感が低下する
- 少しでも難しいと感じたタスクに手をつけられなくなる
- 言い訳作りにわざと下手な時間の使い方をする(セルフハンディキャップ)
- 自己妨害をする(セルフサボタージュ)
- 想起が否定的すぎる場合の戦略
- ネガティブ想起改善シート
- たいていの作業は思ったより簡単で満足度が高いことに気づく
- 手順
- 時間をうまく使えないタスクを選ぶ
- タスクを30〜120秒でこなせるレベルの細かさに分割し、最初の4〜5ステップを書く
- 手順の「予想される困難度」と「予想される満足度」を書く
- 手順が終わるごとに「実際の困難度」と「実際の満足度」を書く
- マイクロ・サクセス
- 日々の小さな成功を意識する
- 1日の終わりに5分程度小さな成功を書く
- アドバイス法
- 同じ目標を持つ人にアドバイスする
- 他者を助けている感覚が、自己効力感の向上につながる
- 空想で他者に助言してみるだけでも効果がある
- リフレクション
- 過去の成功体験を将来に活かす
- 手順
- 過去に成功を収めた経験をひとつ選ぶ
- 思い当たる成功の要因を2〜3個書き出す
- 2で得た教訓を新しいタスクに使って計画を立てる
- ネガティブ想起改善シート
- 生きがいチャート
- 生きがいを探す
- 生きがいのメリット
- 生きがいを持っている人は、ストレスに強く、健康で人生の幸福度も高い
- 脳が没頭状態に入り、時間を忘れさせる
- 生きがいにつながるかで、重要なことの判断がつく
- 手順
- 以下に当てはまるものをリストアップする
- 自分が楽しいこと
- 世間が必要とすること
- 世間から金銭がもらえること
- 自分が得意なこと
- 重複するものを探す
- 生きがいを生み出すために何ができるかを考える
- 以下に当てはまるものをリストアップする
- 文学に親しむ
- 簡単に答えの出ないものに親しむことで、認知の耐性を向上させる
- 集中力を取り戻し、深い思考ができるようになる
- 他人のために時間を使う
- いつもより時間がある感覚を得る
- 人の役に立った自信も得ることができる
- 退屈トレーニング
- あえて退屈なことをしてみることで、日常の些細なことに目が向くようにする
- 普段はスルーするようなことにも注意を向けることで、印象的な想起が増える
- 印象的な想起が増えることで、過去を振り返った時に長い時間を過ごした感覚を得られる
- イベントタイムで過ごす
- 時計に頼ってスケジュールを組むことで、時間に人生をコントロールされている感覚が生まれる(クロックタイム)
- 時計に頼らずイベントドリブンで過ごすことで、時間の余裕が生まれる(お腹が空いたからご飯を食べるなど)
生産性を上げようと思うと、効率的なやり方を追い求めがちですが、逆にそれが生産性を下げることもあるというのは衝撃的でした。。
本では他にも様々な研究結果が紹介されていて、自分の時間感覚タイプを把握しながら読むと、なるほど、、となる知見がたくさん隠されていました。
ぜひ、読んでみてください。
時間感覚タイプテスト
YOUR TIME ユア・タイム: 4063の科学データで導き出した、あなたの人生を変える最後の時間術 鈴木 祐 (著)

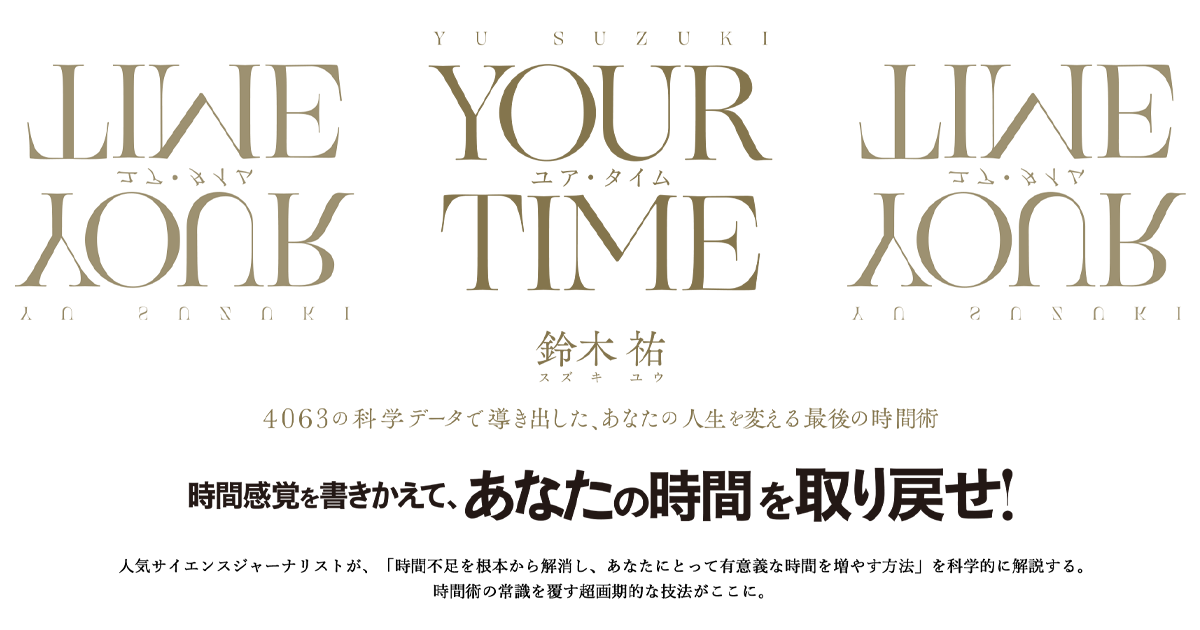
コメントを送る
コメントはブログオーナーのみ閲覧できます